みんなが社会の中で誇りをもって、心豊かで幸せな生活を送ることができるようにならなければなりません。
誇りを持てる「できること」を身につけ、「自分にもできるんだ」という自信や自己肯定感をはぐくんでいくことを大切に考え活動を行ってまいります。
誇りの感情が芽生えると、ほかの人にも興味が出てくるようになりますし、周囲の人とのコミュニケーションの幅も広がります。
何気なく噂を聞きつけたBくんが、
Bくん 「Aくんって、住宅の設計図面が描けるんだって?」
Aくん 「うん、そう。キャドを使って図面を描いたりしてるんだ。」
Bくん 「キャドって何だ・・?」
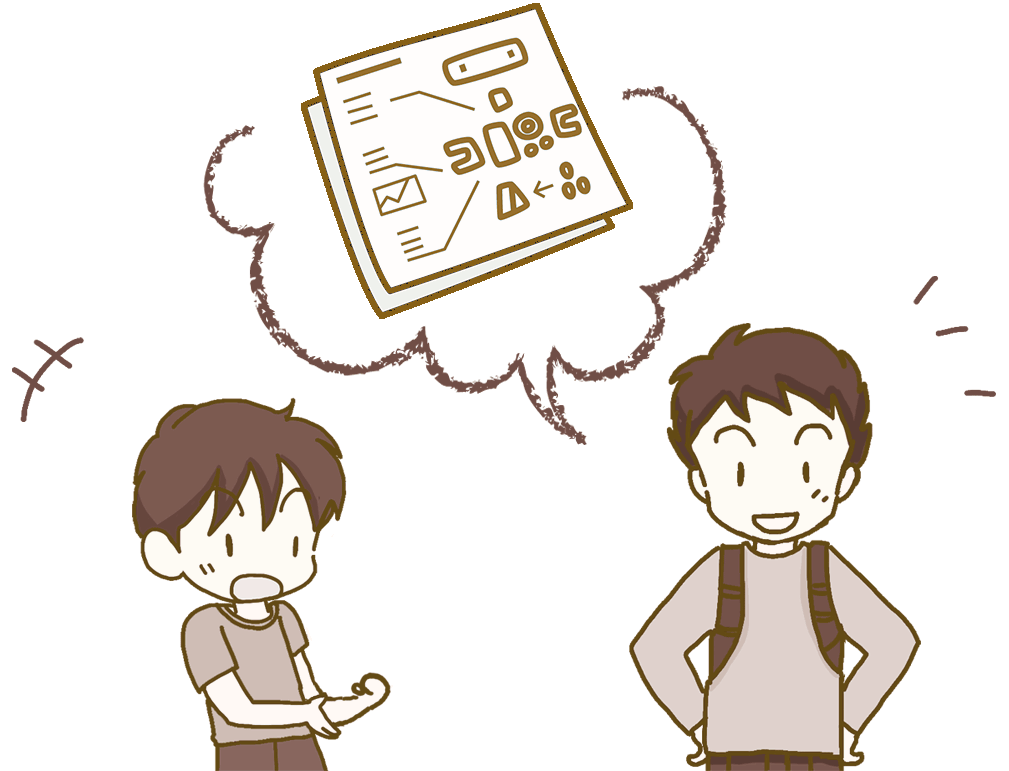
Aくん 「パソコン使っていろんな設計図面を描いたりするソフトなんだ。」
Bくん 「すげえな、むずかしそうだなぁ。」
Aくん 「うぅん、やってみると簡単だよ。」
Bくん 「えぇっ、ほんとかなぁ?」
Aくん 「今度どんなふうにやるのか見せてあげるよ。」
立派なコミュニケーションですよね!
コミュニケーションにおいて、それぞれの立場や心情を思いやり、互いに支えあうことの素晴らしさにふれるような活動を創造していきたいと考えます。
幸せの象徴である「愛」と「豊かさ」を得られるかどうかは、「感謝」を感じる感度によるものです。周囲のいろいろな人・物・事に「ありがとう」と感じる人は、愛と豊かさを感じる感度も高く、幸せ感が高くなります。
感謝の気持ちとは主観的なものです。現実の現象は変わらなくても、自身が好意的・肯定的に受け取るか、敵意的・否定的に受け取るかで、心のありようは大きく変わってきます。
約束を守ること、正直であること、素直であること、裏表がないこと、こうした真っすぐな人間力が「誠実さ」であります。
それは、他人との約束を守ることが仮に守れなかった場合でも、それをしっかりと謝り、状況や代替策をもって誠意を尽くすことも「誠実さ」なのです。
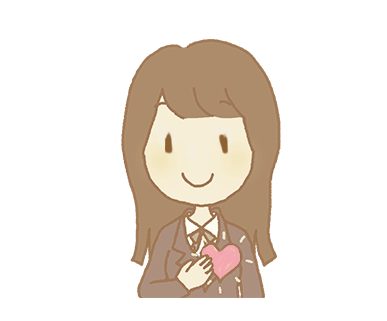
人は他の人たちと接する経験を持つほど、世の中の広さ、先人の偉大さ、他の人間の尊さをより感じるようになります。逆に、社会経験を積むことによって自身でできることが増えていくと、自分の存在を過大に評価し、世界観が狭くなり、高慢な態度をとるようになってしまう事もありがちです。
学ぶことに終わりはないこと、誰からでも学ぶべきものがあることを知る姿勢、それが「謙虚さ」であります。
